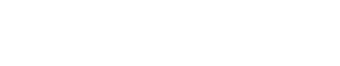第18章 地域主体の生活交通確保へ
目次
規制緩和による全国的な波紋
乗合バス事業に対する国の規制緩和が一段と色濃くなるに従い、全国的な波紋は広がっていった。平成13年11月19日の日本経済新聞は、日本バス協会調べによる平成10年度バス地域別系統数と赤字の割合を掲載し、規制緩和で競争激化、不採算路線は統廃合で「地域の足」消滅の危機と報じた。
この記事によると、「規制緩和前とされる平成10年度の系統数と赤字割合は、北海道2,554路線65.9%、東北2,779路線69.3%、新潟2,035路線76.0%、関東8,840路線66.5%、中部5,240路線72.7%、近畿4,762路線72.0%、中国3,747路線70.1%、四国1,463路線87.4%、九州7,916路線66.3%、沖縄132路線83.3%となっていた。乗合バスはピークの昭和45年ごろには、全国で年間100億人の利用客があったが現在は50億人弱。日本バス協会によると全国にある約40,000系統の7割が赤字であるという。
今年度から赤字バス路線に対する国の補助制度が変わったのも再編に拍車をかける。新制度では、国の補助対象は複数市町村を走る広域的な路線や県庁所在地などに繋がる幹線などに限定。幹線は国、生活路線は自治体と役割分担を明確にした。この結果、過疎地を走る路線は自治体が国の補助金を肩代わりしないと維持しずらくなった。」と記述している。
平成13年11月7日の北海道新聞も地殻変動・道内路線バス事情と題して、特集記事を連載した。
悲鳴「生活の足」、再編「撤退か人件費削減」と見出し活字が目にふれる。「運行を止めることはできない。住民の足をまもるために」北紋バスの和田輝彦社長は労組委員長から一転して経営トップに就任した。親会社であった東急電鉄の持ち株を社員が買い取り自分たちで経営する道だったと例をあげ、生き残りをかけた再編とコスト削減の模索が続くと報じた。
さらに、連載は、共闘「狙われる都市間バス」共同運行で参入を阻止、復活「市町村が路線を開拓」運行管理に民間も呼応と続き、穂別町の小型バスによる「ふれあいバス」の運行例なども紹介している。
また、11月20日には札幌市長の諮問機関「市営企業調査審議会」は、札幌市営バスの全路線を民間のバス会社に移譲すべきと答申するなど規制緩和をめぐる波紋は、新しい補助制度とも連動し道内はもちろん全国各地へと急速に広がっていった。
地域主体の生活交通確保に試練
北海道の乗合バスの輸送需要は、昭和40年代半ばの約6億人をピークとして利用者は恒常的に減少した。過疎化の進行による人口減少やマイカーの普及、都市部における渋滞等走行環境の悪化等が原因とされ、乗合バス事業者のほとんどが赤字経営に苦しみ、厳しい経営状況が続いていた。
この要因の一つである人口動向を見てみると、過疎化の進行は明らかである。昭和45年の北海道の人口は、5,184千人(市部3,432千人、郡部1,752千人)であったが、平成14年では5,667千人(市部4,375千人、郡部1,291千人)と微増した。約30年間で北海道の人口は483千人(9.3%)増加したことになるが、これをよく見ると市部では943千人(27.5%)増加したのに対し、郡部では461千人(26.3%)が減少し都市への人口流出が加速している。特に、札幌市の人口動向をみると、昭和45年の1,010千人が平成14年には1,822千人で812千人(80.4%)の増加となり、札幌市への一極集中が顕著となっている。
これを、輸送人員で見てみると、昭和45年には全道の乗合バス輸送人員が6億3,444万人であったものが、平成13年では2億2,797万人となり、4億647万人(64.1%)が減少し、如何にマイカーの普及が著しいかが分かる。
こうした時流の中で、乗合バスの役割は都市部と地方部で大きく変質した。都市部においては、交通渋滞や違法駐車による走行環境の悪化に伴い交通機関としての信頼性が低下していることや大型ショッピング施設の郊外進出による都市機能の郊外化などにより、乗合バス事業の経営環境の厳しさが増す一方で、地域住民の日常生活を支える公共交通機関としての重要な役割を果たすことが求められた。
地方部においては、過疎地域を中心としてバスの輸送需要が少ないことにより、地域住民が利用しやすいバス路線網の整備や運行ダイヤの設定が困難なことから、さらにバス利用者が減少するという悪循環に陥り、バスの輸送シェアは小さなものとなっていた。しかし、マイカーを利用できない学生や高齢者など地域住民にとっては唯一かけがえのない交通手段であり、その維持は重要なものとなっていた。
このように今後とも都市部・地方部それぞれに重要な役割が期待される乗合バスであったが、平成13年度には制度の大改正が行われた。乗合バス事業も需給調整規制の廃止が行われ新規参入・自由撤退が可能となり、平成12年5月に道路運送法の一部改正が実施された。
これまでの乗合バス事業は免許制を基盤として、路線バスは地域住民の福祉確保の目的に基づき、住民にとって必要不可欠な不採算路線に対しては国と都道府県が2分の1づつを補助することにより生活交通路線を維持してきたが、需給調整規制の廃止に伴い、今後は、国と地方の適切な役割分担のもとに、地方公共団体がより主体的に関与していくことに交通政策が大きく方向を転換した。
人口減少や少子化に加え自由化の影響等により、バス事業者の経営環境はますます厳しくなる一方で、国・都道府県・市町村も財政状況が逼迫していたので、関係者はそれぞれに相当な覚悟を持ち、これまでにない新たな創意工夫を用いながら総力を挙げて取り組まなければ、生活交通の確保を図っていくことは難しい試練の時代を迎えていた。
道運輸交通審議会の答申
このような時代の流れをいち早く察知した北海道は、迅速な対応を図った。平成11年4月の運輸政策審議会自動車交通部会の答申が行われる直前であった3月24日、堀達也北海道知事は、「北海道における乗合バス事業の需給調整規制廃止後の生活交通の確保に関する基本方針について」北海道運輸交通審議会(会長佐藤馨一:北海道大学大学院教授)に諮問をした。
北海道運輸交通審議会は、直ちにバス小委員会(委員長石井耕:北海学園大学教授)を設置し専門的な審議に委ねた。丁度そのころ北海道では、国の運政審自動車交通部会の答申に盛り込まれた「地域協議会の設置」を先取りし全国に先駆けて、8月24日には北海道の14支庁に「地域交通懇談会」の設置を完了していた。バス小委員会は実務作業を進めるため、石井耕委員長など小委員会メンバーによる「生活交通のあり方等ワーキング委員会」を構成し、この地域交通懇談会と連携し意見交換を行い、また、「生活交通の確保等に関する基本方針の考え方(骨子)案」に対する市町村等への意見照会を実施し答申原案をまとめていった。
平成12年12月18日、北海道運輸交通審議会はバス小委員会の原案を基に「北海道における乗合バス事業の需給調整規制廃止後の生活交通の確保等に関する基本方針について」答申を行った。これが北海道における準生活交通路線維持費補助制度の基礎となったものであるので、その概要(要点)を掲載しておこう。
[北海道運輸交通審議会答申の概要]
1基本方向
(1)市町村が主体的に創意工夫により生活交通を確保
ア.「地域が主体的に取り組む」ことを基本として、国・道・市町村・バス事業者等がそれぞれ分担・協調して必要な方策を講じ、地域の実情に応じた効果的な手段により生活交通の確保に当たる。
イ. 様々な創意工夫により地域の足を確保→スクールバスや福祉バスも含めたバス路線の再編等によるバス運行の効率化や市町村営バスの民間委託などに積極的に取り組む。
2バス路線維持のための支援制度
(1)国は、ナショナルミニマムの観点から、広域的・幹線的路線について維持
ア.広域行政圏の中心都市等を起点とし複数市町村にまたがる路線のうち、一定の基準を満たすものについて、国と道の負担により維持
(2)道は、地域的な交通ネットワーク形成の観点から、広域的・幹線的路線について維持
ア.複数市町村にまたがる路線のうち、一定の基準を満たすものについて、道と市町村の負担により維持
イ.一市町村内のみの路線のうち、一定の基準に該当するものに対し支援を検討
ウ.市町村自ら主体的に取り組むバス路線について、道が一定の支援も検討
(3)一市町村内のみの路線等は、原則として市町村の負担で維持
ア.一市町村内のみの路線や市町村自ら主体的に運行に取り組むバス路線については、原則、市町村の責務として維持
イ.バスによる運行が効率的でない場合には、乗合タクシー等バス以外の多様な手段により必要な生活交通を確保
3関係者の協力体制
ア.道全体の協議会と支庁単位(または広域市町村圏単位)の協議会を設置
イ.構成員は、国、市町村、事業者等
4バス利用促進のための環境整備
ア.超低床ノンスッテプバス等の導入、バス専用レーンの設置、冬季における除雪体制の整備による走行環境の改善を図るとともにバスの安全運行を確保
道地方交通審議会の答申
北海道運輸局は、北海道の運輸行政を担っているが、道地方交通審議会等を設置して、より広い視点に立った総合的、効果的な交通行政を展開していた。
道地方交通審議会は、昭和57年から平成2年にかけて、北海道を4つの地域に分けて公共交通機関の維持整備に関する計画を答申していた。
それから10年以上が経過したが、平成12年に21世紀をむかえた日本は、経済活動や社会生活などあらゆる分野で大きな変革期に差し掛かっていた。
交通事業においても、これまで交通サービスの安定的な供給を確保する機能を果たしてきた需給調整規制は、規制に伴う効率性の阻害等の問題や制度的意義が薄れてきたとして、原則廃止の方向で進められ、事業の効率化が求められ始めていた。
人口の都市部への集中と地方の過疎化が進行し、マイカーへの依存度が高まる中で公共交通機関の経営が悪化し、また、急速な少子・高齢化社会の到来が見込まれる中で、個人の価値観の多様化・高度化、環境問題の深刻化、情報通信技術の飛躍的発展など交通を取り巻く社会情勢は大きく変化してきていた。
特に、人口密度が低く地域間距離の長い北海道は、規制緩和の推進も相まって、生活交通の確保が重大な課題となり、経済・社会活動の広域化に対応した交通ネットワークの多様化・充実が求められていた。
平成11年10月、中田洋北海道運輸局長は、こうした状況の変化や課題に対応し、北海道が発展をしていくためには、利用者ニーズに応じた適切な交通サービスの提供が不可欠であり、北海道における交通ネットワーク・公共交通機関のあり方、今後の輸送サービスの向上方策の検討と実施が必要として、北海道地方交通審議会(会長:伊藤義郎)に「北海道における公共交通機関の維持整備に関する計画について」諮問した。
北海道地方交通審議会は、直ちに計画策定部会を設置して部会長に北海学園大学工学部の五十嵐日出男教授を選任した。その後、計画策定部会は9回に及ぶ審議を重ね答申案をまとめ平成13年3月に北海道地方交通審議会の答申が行われた。
この答申は、北海道新世紀公共交通ビジョンとして示されたもので、鉄道・バス・タクシー・旅客船・航空など全ての交通機関を対象とした。その内容は、地域間交通・地域内(生活)交通・都市圏交通・道内外交通の4分野に及び、根底に流れる思想は「いかにモビリティの質を高め、いかに経済、社会及び環境と相乗効果を生み出していくか」にあった。
路線維持補助制度の大改革へ
貸切バス事業に続く乗合バス事業の規制緩和は、昭和47年に発足した「地方バス路線運行維持対策補助制度」をも大きく変えた。
平成11年4月、運輸政策審議会自動車交通部会の答申があり、今後の乗合バス事業に係る生活交通の確保方策は、国と地方の適切な役割分担のもとに、地方公共団体がより主体的に関与していくことが適当であり、国はナショナルミニマムの観点から維持することが適切であると考えられる広域的・幹線的な輸送サービス類型について支援することが適切とされた。
また、主として地方部を中心として、生活交通の確保のための必要な措置等を協議するための地域協議会(仮称)を必要に応じて設置することが適当とされた。運輸省は、この答申を受けて国は新たな補助制度への移行を図っていく必要があるとして、早急に検討を進めていった。
日々の地域生活を支える路線バスを支障なく運行することに腐心し、地域社会の安定と地域経済の下支えをしてきたと自負するバス事業者にとって、規制緩和の渦潮は理解に苦しむところであった。これまでの永い歴史が物語るように、先覚者が汗と涙の苦労を乗り越えて今日の礎を築いてきたことは既存事業者でなければ分からないことであり、公共交通機関としての使命と誇りを糧として厳しい経営環境のなかで経営維持の活力としていた。
広域的・幹線的の範囲や地方自治体の役割分担の範囲及び財源措置など深い霧に包まれた状況の中で、既存事業者は危機感だけが募っていた。
また、「広域的・幹線的な路線」以外は地方自治体が関与することについても、市町村にとっては突然のことであり、困惑と不安とが入り混じり混迷していた。
道バス協会が全国に先駆け要請行動
平成11年11月、道川忠会長は北海道知事への要望書を持ち真田俊一副知事と山口博司総合企画部長に会い、特に、北海道における「生活交通の確保等に関する基本方針」の策定と「公的補助制度の確立」を最重点として要請し、さらに、市町村財源の確保についても自治省(現:総務省)等へ強力な働きかけを要請した。
北海道も地方財政が厳しい中で、生活交通路線の維持確保は道民生活に直結する重要な課題と強く認識していたので直ちに行動を起こした。真田俊一副知事が運輸省、自治省への中央要請行動を行うとともに、堀達也知事は、二階俊博運輸大臣に会い乗合バス事業の規制緩和に関する要望を行った。
その要望内容は、次のように最も基本的なことであり、かつ、切実なものであった。①広域的・幹線的な輸送サービス類型に係る補助制度の設計にあたっては、できる限り多くの路線(系統)が補助対象となるよう配慮するとともに、必要予算を確保すること。②地方公共団体が主体的に生活交通を確保するための安定的な財政支援措置(普通交付税)を講じること。③地域協議会の必要性や制度的な位置付けは、地域の実情に応じた弾力的な運用ができる仕組みとすること。 ④参入、退出について利用者利便等に配慮した安定的な生活交通の確保ができるよう必要な措置を講じること。
道川忠会長は、北海道の迅速な行動に呼応して直ちに乗合バス事業者社長会を招集し、地方自治体をはじめとする関係機関等に対し、業界の結束した対応をすることで意思統一をし、積極的な行動を展開した。
平成12年5月、乗合バス事業の規制緩和に伴う、道路運送法の一部を改正する法律が成立した。運輸省は、乗合バスの需給調整規制の廃止とあわせて生活交通の確保のための枠組みを抜本的に見直すとして、新しい補助制度の創設を検討していたが、その制度概要は未だ明らかにされていなかった。
道バス協会乗合バス事業運営委員会の下山正委員長は、国の平成13年度概算要求の時期が差し迫っているにも拘わらず、新補助制度に係る基本的な事項が明らかでないことから、バス業界として強く懸念される具体的な問題点(①運行系統の考え方、②単位地域における他社運行系統との競合及び自社運行系統相互の競合の考え方、③運行回数及び平均乗車密度の考え方、④市街地部分の補助カット率の撤廃、⑤補助対象事業者の範囲拡大、 ⑥新補助制度と現行制度の施行時期の整合性、)を挙げ、北海道運輸局、北海道へ趣旨説明をして早急な進展を要請していた。この要望は、補助制度を熟知していた下山正委員長の適切な指摘であり、道川忠会長は文書をもって日本バス協会長に善処方を要請した。
これをうけた日本バス協会は、北海道要望に準じた全国的な具体的要望事項を早急に取りまとめ国へ要望していくことにした。そしてこれを具現化するために、日本バス協会は「新しい補助制度に関する検討会議」を設置し、具体的な検討が始まった。
こうして平成12年8月、日本バス協会の地方交通委員会は、運輸省企画課の田中博敏室長を招いて平成13年度バス関係予算要求の概要と補助制度の概要について説明を受けた。この会議で道バス協会からは、①平成13年4月1日から実施される「新しい補助制度」について、地方公共団体に係る新補助制度の創設が間に合うのかどうか懸念しているので、運輸省から都道府県へ一日も早い説明を行い、国・都道府県・市町村の各補助制度が三位一体となって施行されるようにすること。②地方自治体への交付税措置については、バス事業分が現状措置に上乗せになり、バス事業分が明確となるようにすることなどについて強く要請を行った。道バス協会の要請行動は、地方バス路線維持対策補助制度が平成13年3月31日という終着駅だけが示される中で、新補助制度をめぐる周囲は深い霧に包まれ、暗中模索の状態で続けられていった。
9月20日、道バス協会は道川忠会長をはじめ副会長・乗合バス事業運営委員会正副委員長及び各地区バス協会長で構成する陳情団を編成し、道議会自民党役員全員及び党道連役員並びに北海道知事・副知事・総務部長・総合企画部長などに対し「新しい補助制度」の創設について要請行動を起こした。
その内容は、①国・道・市町村の新補助制度は4月1日から同時並行して実施できるようにすること。②道においては国と早急に綿密な連携を図り、道補助制度の内容を早期に決定し、市町村指導の徹底と市町村の新補助制度の円滑化を図ること。③道の新補助制度への積極的な取り組みと、少なくとも現行補助制度を下回らないようにすること。④道の新補助制度の創設にかかる十分な予算措置を講じること。⑤道及び市町村の安定的な財源確保を図ることであった。
この要請行動に、道議会も直ちに反応した。9月26日には道議会自民党が第3回定例道議会の代表質問で、10月3日には道議会民主党が一般質問で知事の考えを質している。
212市町村との連携
このように、新補助制度をめぐる議論が活発化してきていたが、市町村への浸透は冴えなかった。下山正委員長は、今後を左右する重要なポイントは市町村との連携強化であると強く認識していた。10月13日乗合バス事業運営委員会では、特にこの点が議題となり全道の市町村へ要望書を送付するとともに、各バス事業者が直接市町村を訪問してバス事業の現状や今後の対応方策等を説明し連携を図っていくことが確認された。
平成12年10月、道川忠会長は212の市町村長へ「生活交通の確保に関する要望書」を一斉に送付した。その内容は、①国及び道の新しい補助制度の内容と地方自治体への財源措置が明確でない段階であるが、平成13年4月からの新制度が円滑に行われ、地域住民の生活交通の確保が図られるよう、市町村補助制度及びその予算措置を講じること、②バス事業者が訪問し説明を行うことへの支援と指導要請であった。
道バス協会の行動に理解を示していた道交通企画課は、国の新しい補助制度の概要が示されてきたことをうけ、11月7日の石狩地域交通懇談会を皮切りに順次各地域の交通懇談会を開催していった。この一連の動向によって、市町村の認識が目覚め始めた。これまでは、国と道との地方バス補助制度が主体となって維持されていた生活交通路線が、広域的・幹線的な路線以外は地方自治体が主体的に維持することで、市町村を巻き込む形での補助制度に移行したことに市町村の困惑が広がっていたことは無理からぬことでもあった。
ともかく、地域懇談会での論議や道バス協会及び各社の要請行動によって市町村の生活交通に対する理解が深まっていく一方で、財源措置とされる市町村への特別交付税措置については確信が持てず市町村は苦悩していた。
第45回全国バス事業者大会が札幌で開催
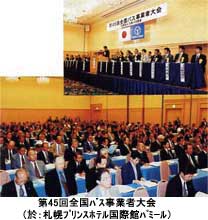
平成12年10月3日、第45回全国バス事業者大会が札幌プリンスホテル国際館パミールで開催された。北海道での全国バス事業者大会は、9年ぶりで全国から約400名が参加した。
この大会は、新しい補助制度の行方が喫緊の課題であったことから、参加者の強い関心が持たれていた。日本バス協会長挨拶、運輸大臣(縄野克彦運輸省自動車局長)・北海道知事(石子彭培公営企業管理者)・札幌市長(小林敏美総務局理事)の祝辞に続いて講演があった。鈴木久泰運輸省旅客課長が「改正道路運送法の施行にむけて」、各務正人運輸省企画課長が「新しい補助制度と来年度の予算要求について」、社団法人北海道観光連盟の我孫子健一会長が「北海道の観光について」と題したそれぞれの講演に参加者は真剣に耳を傾けた。
この中で各務正人企画課長は、広域的・幹線的な路線の考え方にふれ「広域行政圏の中心都市等」にアクセスする路線等の範囲に関して説明を行い、社会生活を維持していくうえで複数市町村をまたぐ路線で一定の中心的な都市へのアクセス、高校など生活上やむをえざる施設へ公共交通機関を使わなければならないなど実質的な要件をもつ都市を考えていることが明らかとなり、参加者に安堵をもたらした。
大会終了後、全道7方面への視察旅行は243名が参加し、北海道観光の人気の高さをうかがわせた。旅行中はまれに見る好天に恵まれ、行く先々で北海道遺産にふれる参加者は北海道の魅力を満喫して離道し、大会は盛会裏に終了した。
道路運送法政令の施行と新補助制度の予算内示
乗合バス事業に係る道路運送法の一部を改正する法律は、平成12年5月26日に公布されたが、これに関連する政令は12月22日に公布され、平成14年2月1日から一斉に施行されることになった。これで2年前に施行された貸切バス事業とともに、法的にはバス事業の全てが新制度への移行を完了したことになる。
12月20日運輸省は、平成13年度自動車交通関係予算内示の概要を明らかにした。平成13年度の地方バス路線維持費補助制度は、事業年度(10月1日~9月30日)と補助年度(4月1日~3月31日)との関連で、旧制度分と新制度分とが混在する形でスタートすることになった。
また、地方自治体に対する財源措置は、生活交通確保対策に必要な経費に対する地方交付税措置として、半年分に相当する事業費規模で460億円が計上された。これで、一応の骨格は示されたことにはなるが、具体的な内容は依然霧の中にあった。
運行系統競合路線の補助金カット
平成13年4月道バス協会は、ようやく示された国の新補助制度「バス運行対策費補助金交付要綱(案)」の補助基準においてバス運行系統の競合区間における補助金カットが示されたため、平成12年度の状況をもって試算を行った結果、補助金カットの影響が極めて大きく地域の生活交通路線確保に重大な支障を生じることが明らかとなった。
これは、かねてから下山正委員長が自社路線の競合と他社路線の競合の違いなど複雑な現状の中で懸念を抱き問題提起を行い内部議論がされていたものであった。
道川忠会長は、下山正委員長の報告をうけ直ちに緊急要請を行うことを決断した。
4月5日、道川忠会長と下山正委員長は、中本光夫北海道運輸局長と石﨑仁志自動車部長に直接会い、国土交通省(運輸省は国土交通省に統合されていた。)への働きかけを要請した。また、堀達也北海道知事に対しても同様の要請行動をとるとともに、日本バス協会会長代行あて緊急要望書を提出した。
その要望内容は、自社における運行系統は地域の実情と輸送需要に適切に対応し効率的な運行を行うよう運行系統を設定しており、本来的な競合とは異なるので自社競合を除外すること等であった。
4月13日道川忠会長は、乗合バス補助対象会社の緊急社長会を招集した。5月8日には日本バス協会地方交通委員会で国土交通省から新補助制度に関する説明が予定されていたことから、直接、国土交通省へ代表団により実態を訴えることが緊要との結論に達し要請行動を行うことになった。
4月19日、代表団は、道川忠会長をはじめ各地区代表など総勢9名が上京し、国土交通省の高橋朋敬自動車交通局長・岩崎貞二総務課長・鈴木久泰旅客課長に要望するとともに、各務正人企画課長・田中博敏生活交通対策室長と会い大きな路線図を広げながら具体的な質疑応答で要請は約2時間にも及んだ。
なお、この要請には日本バス協会桜井勇理事長及び太田満常務理事も同行した。
また、翌20日には北海道も動いた。知事要望書をもって相馬秋夫総合企画部長と市岡卓企画課長が国土交通省へ要請している。さらに、北海道運輸局も石﨑仁志自動車部長が北海道の実情等を上申した模様であった。
このように官民あげての要望に、5月16日、国土交通省は慎重に検討をした結果として、自社競合を除外することはできないが、「輸送量が1日当たり150人を超える競合区間が、運行系統の50%を超える場合に、その割合に応じて補助額をカットする。」と統一解釈を明らかにした。
これによって、一部の地域を除き、北海道全域における大部分の地域は補助額カット額の影響が少なく生活交通路線が救済されることとなった。そしてこのことは、北海道の官民挙げて率先した行動が、結果的には全国的にも大きく貢献をしたことになった。
国会議員・道議会議員の支援
日本バス協会は、道路運送法改正案等の骨子案が次第に明らかとなるに呼応し全国的な対応を始めていた。特に、政治的な支援を得ることが重要と判断し自由民主党への働きかけを強めていたところ、平成11年12月、自由民主党の亀井善之衆議院議員が発起人代表となって呼びかけた「自民党バス議員連盟」が発足した。
平成14年11月現在の参加議員は104名であり、役員は次のとおりである。<顧問>奥野誠亮、林義郎、森喜朗、関谷勝嗣、中村正三郎、堀内光雄、<会長>亀井善之、<副会長>川崎二郎、<幹事長>武部勤(北海道)、<幹事>村田吉隆、林幹雄、渡辺具能、若林正俊、荒井正吾、<本道関係議員>武部勤、岩倉博文、金田英行、北村直人、佐藤静雄、中川昭一、吉川貴盛、中川義雄の各代議士であった。
以後、この「バス議連」(略称)は、バス交通政策の推進に大きな役割を果たしていくこととなった。
平成13年4月、道バス協会は自民党・道民会議北海道議会議員会の役員と正副会長及び乗合バス事業運営委員会正副委員長との懇談会を開催し、バス問題に関する要望と意見交換を行った。これが、その後の「地方バス路線確保対策議員懇話会」へと繋がっていくことになった。
10月1日、北海道議会自民党・道民会議は、地方バス路線に対する国の補助制度の大幅な改正に伴い、北海道としての地方バス路線確保と赤字路線に対する補助のあり方について、関係議員による自民党としての方針をまとめていくため、「地方バス路線確保対策議員懇話会」を設立した。
構成メンバーは、次のとおり自民党役員のオールスターキャストで構成され、全国初の都道府県「バス議員懇話会」が誕生した。
平成14年11月現在の参加議員は、次のとおり15名の役員構成となっている。会長:和田敬友(議員会会長)、副会長:佐藤時雄(党道連総務会長)、幹事長:釣部勲(党道連政調会長)、委員:神戸典臣(党道連幹事長)高橋一史(新幹線・総合交通対策特別委員長)、清水誠一(党道連幹事長代理)、加藤唯勝(議員会幹事長)、丸岩公充(議員会筆頭副会長)、大谷亨(経済委員会副委員長)、原田裕(政策審議委員長)、川尻秀之(総合開発調査特別委員長)、高橋文明(党道連副会長)、酒井芳秀(道議会議長)、加藤礼一(党道連政調会筆頭副会長)、伊東良孝(前政策審議委員長)の自民党各道議会議員であった。
とくに、北海道が深く関わる準広域的・幹線的な路線等については、準生活交通路線補助を恒久的な制度とするためにも政治的なバックアップが必要であり、この「バス議員懇話会」の支援によって財政逼迫の中で時節毎の困難を乗り切ってきたことは特筆すべきことであった。
道生活交通確保対策協議会で審議
国土交通省は、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するための枠組み作りとその他の生活交通について審議し、具体的な路線に係る生活交通の確保に関する計画を策定するために、地域協議会の設置を指導していた。
北海道は、全国の4分の1を占める広大な面積のなかで地域生活を維持しているため、14の支庁を設置して道行政を推進していた。こうした背景をうけて地域協議会の設置については、各支庁ごとに支庁協議会を設けるとともに、支庁協議会への指導助言や生活交通の確保に関する制度等のあり方に関する事項の協議を行うため、平成13年3月に北海道生活交通確保対策協議会を設置した。また、この全道協議会は、各支庁協議会の結果を取りまとめ全道の生活交通確保に関する計画を策定する役割も担っていた。
その構成は、国土交通省の告示によって少なくとも関係都道府県、関係市町村及び関係地方運輸局の長又はその指名する職員並びに関係旅客自動車運送業者とされていたが、北海道においては関係労働組合代表者も参加していた。北海道における地域協議会の設置がスムーズに進んだ背景は、既述したとおり規制緩和に関する中央の動きをいち早く察知した北海道が、平成11年1月から各支庁ごとに地域交通懇談会を設置していたので、これを衣替えする形で一気に支庁協議会への設置が進んだことによる。
北海道生活交通確保対策協議会は、各支庁協議会での様々な問題を調整して平成14年6月に平成14年度から16年度までの生活交通路線維持確保3ヵ年計画を策定した。これによると、平成13年度と平成14年度の系統数とキロ程数は下表のとおりである。
生活交通路線の概要
| 区分 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 系統数 | キロ程数 | 系統数 | キロ程数 | |
| H13計画 | 176 | 7,441.3km | 174 | 7,417.9km |
| H14計画 | - | - | 192 | 8,472.4km |
| 増減 | - | - | 18 | 1,054.5km |
準生活交通路線の概要
| 区分 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 系統数 | キロ程数 | 系統数 | キロ程数 | |
| H13計画 | 105 | 2,781.1km | 91 | 2,102.4km |
| H14計画 | ー | ー | 88 | 2,012.0km |
| 増減 | ー | ー | △ 3 | △ 90.4km |
(注)14計画(新制度)は3ヵ年計画であるが、平成15年度・16年度は省略した。
市町村生活バス路線の概要
| 区分 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 系統数 | キロ程数 | 系統数 | キロ程数 | |
| H13計画 | 149 | 3,439.7km | 153 3,581.0 | ー |
| H14計画 | ー | ー | 155 | 3,604.1km |
| 増減 | ー | ー | 2 | 23.1km |
(注)14計画(新制度)は3ヵ年計画であるが、平成15年度・16年度は省略した。
市町村単独路線の概要
| 区分 | 平成13年度 | 平成14年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| 系統数 | キロ程数 | 系統数 | キロ程数 | |
| H13計画 | 352 | 9,179.8km | 336 | 8,425.6km |
| H14計画 | ー | ー | 395 | 8,986.0km |
| 増減 | ー | ー | 59 | 560.4km |
(注)14計画(新制度)は3ヵ年計画であるが、平成15年度・16年度は省略した。
新旧補助制度の混在でスタート
新しい補助制度は、乗合バス事業の規制緩和に先だち前倒しで実施することになった。
これまでの補助制度は、乗合バス事業の事業年度を10月1日から翌年の9月30日までとし、この期間を補助対象としていたが、新しい補助制度では、国の会計年度との関連から平成13年4月1日からの適用とされた。
このため、平成13年度の地方バス路線維持費補助制度は、平成12年10月1日から平成13年3月31日までの旧補助制度分と平成13年4月1日から9月30日までの新補助制度分とが混在する形でスタートすることになった。
各バス事業者の事務処理は繁雑を極めた。一事業年度を単に旧制度分と新制度分に二分割するという単純なものではでなく、加えて新補助制度基準に適応した路線再編等様々な課題にも直面した。
バス事業者は平成14年から16年度までの生活交通路線維持確保3ヵ年計画の策定に間に合わせるべく、路線の再編と補助制度の創設など関係市町村との折衝も急を要した。
一方、関係市町村も同様であった。各市町村の財政状況が極めて厳しい状況の中で、交通担当セクションも困惑し、バス事業者との調整折衝が難航したところが多かった。しかし、地域住民の生活交通の維持確保という大義は、双方の譲歩を求めながら次第に支庁協議会の場で結集されていった。
道補助制度の暫定措置で一息
バブル崩壊、デフレ経済の進行に引き続き、後述する米国における同時多発テロ事件等の影響もあり、世界経済が同時的に減速するなど、日本の景気が一段と悪化する中で、国の財政も地方公共団体の財政も厳しい状況に置かれていた。したがって道財政はこのような状況の変化に対応し各種政策を見直し緊縮型へと検討を始めていた。
一方、このような時代背景の中で乗合バス事業の規制緩和が進められ、これに伴う新しい補助制度は、国と地方の適切な役割分担に基づき、地方公共団体がより主体的に関与することになっていた。道は、こうした厳しい財政環境の中で新しい補助制度への移行期に伴う経過措置として、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの当面1年間に限定した補助基準の緩和措置を講じた。
道バス協会は、この経過措置が特例的に平成13年度の1年間の期間限定とされていたことから、危機感をもってこの経過措置の恒久化を求め陳情団を編成して要請行動を展開した。
平成13年11月7日、豊島弘通副会長を団長とし乗合バス事業運営委員会正副委員長及び各地区バス協会長等で構成する陳情団は、道議会自民党和田敬友議員会長をはじめ自民党各役員へ要望を行うとともに、藤井章治副知事・高尾和彦総務部長・相馬秋夫総合企画部長・日野健一交通企画室長などへ陳情要請を行った。
このなかで、藤井章治副知事は「道財政の厳しい現状にあるが財政の論理だけで捉えてはならない。きめ細かい配慮も必要である。厳しいけれど検討する。」と答えたが、これは厳しい財政環境と道民生活への配慮という比重配分に苦慮する現状を如実に表現していた。道バス協会は、さらに自民党道連及び民主党道民連合議員会へと要請の範囲を拡大していった。
こうした一連の要請行動もあって、道は準生活交通路線維持費補助制度については恒久的な補助制度の実現には至らなかったが、平成13年度の経過措置について一部見直しをした上で平成15年度までの暫定措置として2年間延長されることになった。また、バス事業者が撤退後、市町村の自主運行や貸切バス事業者への運行委託などにより、市町村が自ら代替バスの運行を行う場合に市町村に対し道が補助する市町村生活バス運行費補助制度についても継続された。
しかし、平成16年度からは、これを廃止する方向が示されており、恒久的な補助制度への道のりは極めて厳しい状況にはあるが、まずは一息をついた形となった。