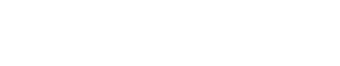第5章空襲下に路線確保
目次
戦時統制さらに強化
戦線は拡大し過ぎ、アリューシャン列島アッツ島で守備隊約5千人が玉砕した昭和18年、国内の自動車輸送力を戦時の要請にこたえられる態勢とするため、自動車交通事業法の第二次改正が行われ、各自動車運送事業組合は統制組合の性格を強化された。
このため全乗連(全国乗合自動車運送事業組合連合会)の業務の大半は、まず代用燃料や部品の配給、そして潤滑油確保のためヒマの自主栽培(鉄道省の指導のもと、陸運ヒマ栽培指導協会が栽培、供出をし、軍から廃油の還元を受けて精油して業界に配給するシステム)などに主力が注がれた。
タイヤ、チューブなどの部品はすべて戦力資材と競合するので、その入手は困難をきわめ、これはトラック、乗用車業界にとっても同じだったから、3業界の連合会が共同で物資の需給取り扱いに当たることになり、三連物資部として関係各省との連絡、情報の収集、配給事務等を一括して行った。
昭和18年10月ころ、連合会と鉄道省が関係した自動車関係の資材の配給は、次のように広範な部門にわたったと記録に残る。
1、車両=4半期ごとに行われるニッサン、トヨタの車両の配給について鉄道省と商工省が協議決定し、販売承認が指令される。
2、揮発油=燃料局から地方庁を通じ購買券が発行される。
3、燃料=木炭、薪、石炭、カーバイト、コーライト、液化ガス、天然ガス、石炭ガス=商工省から地方庁を通じ指示される。
その他、全乗連が担当した物資には油脂、制動油、蓄電池、タイヤ、チューブ、モケット、清浄布、方向幕、ラッカー、被服、地下足袋、ゴム長靴、用紙など、あらゆるものにわたっている。
北海道の事業組合の場合も同様、輸送の確保のため、何でも屋のような努力が続けられた。すでにバスの9割が木炭車であったが、配給制の木炭の現物が不足し、事業組合や各社は薪炭組合を組織し、自家生産の形で確保して運んだが、闇屋と間違えられて取り締まりの網にかかることもしばしばだったという。潤滑油の入手も難しく、モービルやグリースの代用に魚油や海獣の脂を利用したところもあった。
バス事業者は配給、独自開拓のルートを問わず、懸命に資材を確保し、細々と営業を継続したが、年々休止路線は増え、サービスの低下、輸送量の減退はどうしようもなかった。バスの窓ガラスやライトが破損しても補充資材がなく、ベニヤ板を張ったり、廃車の部品で間に合わせるなど工夫が必要だった。戦争遂行のための要員と重要物資輸送のほかにはバスを用いるな、バスがなければトラックに乗せればよいという、バス事業にとっては最悪の事態が来ていた。
大ナタで休止路線を決定
全道7地区への大統合(他に2市営)という、かつてない荒療治によるバス業界の再編をともかく終えたのは昭和19年であったが、その1月の初めには米軍がフィリピンのルソン島に上陸し、戦局はいよいよ敗色を深めていた。2月25日、宮中で開かれた閣議は「決戦非常措置要綱」を決定した。その内容は学徒勤労動員の強化、徴用制・特に女子挺身隊の強化、高級料理店・遊興機関の廃・停業、疎開の徹底などであったが、このなかの柱のひとつとして、バス路線の徹底的な規制があった。
その要項は(1)軍需生産要員の輸送確保と、戦力増強に関係のない輸送の徹底抑制(2)路線整理、運行計画の再検討(3)貨物自動車による旅客輸送(4)その他設備、資材の能率化を柱として挙げている。
その具体的な方策としては、学生と工員の通勤路線・食糧増産・重要物資開発路線等の確保と鉄道併行路線・遊覧路線・買い出し路線・交通量希薄または3km以内の路線の休廃止もしくは回数の縮減、さらに停留所間の距離は2km以上とし、通勤時には一般客の利用停止、重要輸送には貨物自動車の人員輸送を認め、遊休能力・要員の貨物輸送への転用などを指示していた。
この通達は北海道警察部を経て、北海道乗合自動車運送事業組合に伝達された。バスの運行を真に必要な路線のみに規制し、しかもその運行回数を最小必要限度に止め、その他の路線は全面休止という文字どおりの非常措置であった。
いわば、民生路線である毛細血管への栄養補給を断ち、戦争遂行に必要な動脈だけに血液を送るという決断だけに、どの路線を休止し、どの路線を維持すべきか、裁断は事業組合と警察部の間で緊密な検討が繰り返され、ようやく6月2日付で「決戦非常措置に関する件」として通知が出た。
古めかしい候文によるこの指示の骨子を読みやすくすると 「旅客自動車運輸事業決戦非常措置として、昭和20 年3月末日まで、別紙区間以外の旅客自動車運輸事業を全面的に休止せしむることに決定相成(あいなり)候条、従来の事業計画にして変更(運転系統、発車時刻)を生ずるものはその手続きを履行せしめ、その他の路線に対しては、すでに休止許可せられたるもののほか、差し当たり昭和20年3月末日まで休止願提出せしめ、緊要性なき短距離停留所を整理し、輸送力増強を図る等、万遺漏なきを可被期(きせらるべし)」 というものであった。別紙には7地区2市営バスの「生き残り路線」が示されており、いわば栄養失調で痩せこけ、貧血事態なった非常時道内バス輸送の貴重な記録なので、別項にその全部を採録する。(詳細は〔決戦非常措置残存路線〕に)
路線への大ナタが振られる前、すでに車両も燃料も、そして乗務員自体もすべて不足していた。車両は代用燃料車ばかりとなり、木炭、薪用のかまを背負って、気息えんえんとした運行ぶりで、坂道にかかるとお客さんに押してもらってやっとはい上がるという状態が続いていた。
さらに19年6月にはサイパン島で守備隊3万人が全滅し、児童の集団疎開が始まり、7月、東条内閣が辞職した。この年、陸運統制令が改正され、自動車の譲渡、貸し渡し、廃業は禁止された。経済全般にわたって国の統制カはさらに強められ、民間の活動は窒息寸前の状態となった。
人手不足から女性運転手が登場

戦争の激化にともない、各社の従業員から応召、徴用者が増え、乗務員、整備員の不足が問題になってきた。これは産業全般にとっても同様で、大学生から旧制中学生、女学生まで、男女を問わず、学徒勤労動員や女子挺身隊などの名目で徴用が進められたが、技術を要する職種だけにバス業界の悩みは深刻だった。そこで北海道乗合自動車運送事業組合は昭和19年から女性運転手の養成に乗り出し、各社に配置した。
女性運転手の活躍ぶりに触れている「北海道中央バス五十年史」から紹介しよう。
「当社では女子車掌の中から適任者を選んで運転免許を取得させ、小樽に八名、札幌に五名配置した。しかし速成教育で免許を取ったばかりの非力な彼女らにとって、男でも難しい木炭車の取り扱いは大変な仕事だった。当時の木炭車はほとんどセルモーターをはずしていたため、エンジンを始動させるには重いクランク棒を力いっぱい何回も回さねばならず、運転中にパンクしたり、エンジンが故障したりすると、もうおてあげ状態、運転未熟のため車体をあちこちにぶつけることも多く男の運転手仲間から『女子特攻隊』などとひやかされていた。
しかし彼女たちは未熟とはいえ、みな真剣に職務に励み、当社の業務に大きく貢献した。彼女らが活躍したのは終戦前後の二、三年で、やがて『私たちの役目は終わりました』と全員が自発的に退職を申し出、姿を消していった」
当時、交通関係で男性の職場に女性が進出して活躍した例では、函館市電の女性運転手さんもそうであった。また「中央バス五十年史」は学徒動員などにも触れている。
「当社では整備員不足をカバーするため、昭和20年に道庁を通じて学徒動員を要請、これに応じて庁立小樽商業学校(現道立小樽商業高校)の男子生徒10 名が、小樽整備工場に整備員助手として配置された。彼らはよく働いたが、車に興味を持つ年ごろだけに、すきをみてバスを運転したがるので、管理者は彼らが無免許運転しないよう、そして作業中に事故が起きないよう気を配るのに大変だった。
また木炭バスのガス発生炉の掃除や木炭割りなどの作業に、各営業所では近くの農漁村から男女労務者を雇ったが、この人たちは真っ黒になってよく働いた」
当時、前線に対して、直接戦闘に加わらない後方のことを「銃後」と呼んだが、人も資材も不足する銃後の仕事と暮らしも苦難に満ちていた。そして本土への空襲が激しくなり、銃後は前線と等しくなった。
室蘭空襲でバス従業員が殉職
昭和20年に入り、日本本土へのアメリカ空軍の空襲は激しさを増し、3月10日にはB29爆撃機の空襲で東京は焦土と化した。4月になると、完全に本土の制空権は奪われ、B29の空襲は本州全土の都市に広がった。北海道でも空襲は函館、室蘭、釧路などに及んだが、軍需工業地帯・室蘭への攻撃はひときわ激しく、道南乗合自動車(現・道南バス)ではついに従業員の犠牲を出すに至った。「道南バス七十年史」には痛ましい状況が詳しく記述されており、その一部を転載して当時を偲びたい。
「新会社創立当時の所有車両は90台であったが、資材不足のため実際に運行できたのは昭和18年7月で 65台(室蘭33、登別13、洞爺13、日高6)に過ぎなかった。この頃になると、太平洋戦争の戦況は悪化し、わが国にとって深刻となりつつあった。当社から軍隊に召集された男子従業員は48名にものぼり、全従業員にしめる割合は20パーセントを超えていた。しかも、召集された者の大部分が運転者や整備員などで、その補充は難しく、運行業務に大きな支障を生じた。(中略)
決戦非常措置は昭和20年3月までに実施することが通知された。当社に対しては、室蘭市内の主要路線は「軍需工業地帯」という特殊性から認められたが、その他の営業地区は大幅に削減され、総体では路線数が半分以下の15路線、総延長路線は70%弱の 271.4kmにとどまった。しかも1日の運行時間や日数が厳しく規制されたから、運行キロ数は激減して月間4万5千kmを割り、乗車人員も30万人に過ぎず、、その結果は大幅な収入減になったのであった。昭和 19年の暮れから日鐵のガス供給が減少した。これは、満州産の石炭の入荷が止まり、夕張炭に切り替えたためで、当社としては室蘭地区についても大幅に木炭車に切り替えるなどして対応した。(中略)
B29が室蘭上空に現れたのは昭和20年6月下旬であったが、それ以後たびたび飛来しては偵察を繰り返した。このことから、当社も空襲は避けられないと判断、室蘭市内運行バスの一部を日高や洞爺方面に疎開させ、車体はことごとく迷彩を施し、また空襲されたときの乗客の避難誘導訓練を繰り返しながら運行を続けた。
7月1日、多数の戦艦、航空母艦を主軸とするアメリカ機動部隊は、フィリピンのレイテ島を出発した。この機動部隊は、演習を繰り返しつつ本土東部海域を北上し、本土に対する空襲や艦砲射撃を行なった。機動部隊は7月14日、北海道南方の海域にいたり、そこから艦載機を飛ばして北海道全域と東北地方を空襲、また、釜石の製鉄所を艦砲射撃した。そして翌15日、ミズリー、ウイスコンシン、アイオワなどの超大型戦艦、ディトン、アトランタなどの巡洋艦、さらに9隻の駆逐艦から編成された米軍艦隊は、9時30分から約1時間にわたり室蘭の工場地区を艦砲射撃した。
空襲によって室蘭は、港内では多くの船舶が沈められ、港湾設備が破壊されて死傷者が出、また艦砲射撃などによって5百余名が死傷し、日鐵、日鋼の工場や、御前水、輪西、中島町などの民家が大きな被害を受けた。道路や水道も直撃弾などで被害を生じ、御崎から輪西までの道路は不通となり、各工場の機能はまったく停止した。
14日早朝の空襲警報発令により、当社も市内バスを退避させ、本社は徳中社長以下が社屋にあって各地と連絡し指示を行なっていた。そのうちに敵機が本社上空に現われ、本社社屋を攻撃した。そのため従業員の嵐猛整備員は正面玄関で敵艦載の機銃掃射を受け、殉職した。殉職した嵐猛整備員は責任感が強く、すぐれた技能を持ち、整備部門の中心的存在であった。享年37歳。遺骸は空襲の間隙を縫って本町の自宅に運び、徳中社長が葬儀委員長となって社葬を行なった。空襲及び艦砲射撃の混乱の中、当社が創立して初めての殉職社葬であった。
日高方面でも岩志内でバスが艦載機の攻撃を受けたが、ガラスが破損した程度で人命に異常はなかったという。
艦砲射撃により、市内の交通は事実上マヒ状態となってしまった。その夜は、着の身着のままの姿で、伊達あるいは登別方面に徒歩で避難する人たちの列が続いた。次の朝早くから警戒警報が発令され、『艦砲射撃の恐れあり』との情報も流れたが攻撃は無かった。その後、B29による偵察がしつように続き、市民は次に行なわれるであろう大がかりな空襲や艦砲射撃におびえながら毎日を送った」
以上が「道南バス七十年史」に記された7月14、15 両日の大空襲を中心とするなまなましい記録だが、米軍機は室蘭のほか道内の重要拠点都市を集中的にねらい、被害は釧路、根室、函館、帯広などを合わせ死者835人、家屋被災4274戸に及んだ。とくに函館では、本州と結ぶ動脈の青函連絡船が攻撃され、12 隻のうち8隻が沈没、4隻が損傷して全滅という手痛い打撃を受けた。
やがて8月6日広島、9日長崎と原子爆弾が投下され、9日にはソ連が参戦して満州や樺太、さらに千島を攻撃した。8月15日にいたり、日本政府はポツダム宣言を受諾、無条件降伏した。この先どうなるのか、だれにもわからなかったが、道民は空襲におびえながらの灯火管制という真っ暗闇の生活からだけは解放された。しかし、バス業界にはこのあともしばらく苦難の戦後が続いた。
決戦非常措置残存路線
(起点、カッコ内経過地、終点、延長km、運行回数、摘要の順)
1、北海道中央乗合自動車株式会社
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 寿都原歌 | 34.7km | 2回 |
| 蘭越(島古内)湯別 | 39.5km | 2回 |
| 岩内盃 | 19.5km | 4回 |
| 余市赤井川 | 15.5km | 3回 |
| 古平余別 | 35.6km | 1回 |
| 余市駅余市神社 | 5.0km | 10回 |
| 豊平(月寒)二里塚 | 5.9km | 53回 |
| (豊平月寒間は折返し運行、月寒二里塚は2往復のみ) | ||
| 札幌石狩 | 24.0km | 14回 |
| (札幌茨戸間5往復運行、札幌石狩間9往復運行。連行共) | ||
| 厚田石狩太美 | 32.1km | 4回 |
| 長沼由仁 | 8.6km | 3回 |
| 月形岩見沢 | 24.5km | 3回 |
| 美唄三井美唄炭山 | 4.0km | 14回 |
| (近距離かつ鉄道あるも特殊事情に依る) | ||
| 滝川茂生 | 64.5km | 1回 |
| 小樽余市 | 18.6km | 6回 |
| (3往復は余市まで通し運行、3往復は蘭島まで運行。全線運行は赤井川連絡に依る) | ||
| 小樽市内線 1号線 | 3.9km | - |
| 同2号線 | 4.6km | - |
| (スズラン街より折返し運転) | ||
| 同3号線 | 2.8km | - |
| 同4号線 | 6. 3km | - |
| (洗心橋より折返し運転) | ||
| 同9号線 | 1. 8km | - |
2、函館乗合自動車株式会社
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 万代町(湊)七重浜 | 3.5km | 25回 |
| 同(宮前町)亀田村山下 | 7.4km | 5回 |
| 若松町(宇賀浦町)湯ノ川 | 6.9km | 6回 |
| (下海岸線連絡のみ) | ||
| 戸井(日浦)古武井 | 17.4km | 4回 |
| 古武井椴法華 | 7.7km | 2回 |
| 湯ノ川(石崎汐首)戸井 | 22.6km | 6回 |
| 鹿部(臼尻)尾札部 | 22.4km | 4回 |
| 函館(大野)渡島大野 | 16.8km | 8回 |
| 江差(相内沢)関内 | 51.7km | 4回 |
| 同(我虫伏木戸)渡島大野 | 60.0km | 2回 |
| 関内(貝取村)久遠 | 21.0km | 2回 |
| 久遠(若松)真駒内 | 35.2km | 2回 |
| 江差石崎 | 26.8km | 2回 |
| 江良町松前 | 20.7km | 3回 |
| 松岡吉岡 | 16.0km | 3回 |
3、道南乗合自動車株式会社
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 室蘭本社前(海岸町)祝津町 | 3.4km | 47回 |
| 同(御園町)輪西 | 6.3km | 111回 |
| 輪西町(中島町)知利別 | 5.7km | 75回 |
| 同(同)本輪西 | 6.2km | 25回 |
| 登別駅(中登別)登別温泉 | 7.5km | 9回 |
| (運行時間に依り増車の必要あり、一日運行回数15回とす。連帯線のため) | ||
| 洞爺湖温泉(入江)虻田駅 | 9.1km | - |
| (運行時間に依り増車の必要あり、一日運行回数7回とす。連帯線のため) | ||
| 同(壮瞥)伊達町 | 18.5km | 2回 |
| (一部鉄道併行なるも特殊事情に依る) | ||
| 伊達町(久保内)硫黄山 | 29.7km | 1回 |
| 留寿都(真狩)狩太 | 20.7km | 3回 |
| 平取(振内)岩知志 | 26.7km | 3回 |
| 日高村(占冠)下金山 | 44.0km | 1回 |
| 静内御園 | 14.0km | 3回 |
| 歌笛(本桐)鳧舞 | 8.9km | 2回 |
| 日高村(岩知志)平取 | 44.8km | 1回 |
| 室蘭市(幌泉村)登別村 | 25.9km | 2回 |
| (鉄道併行なるも特殊事情に依る) | ||
4、帯広乗合自動車株式会社
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 帯広(止若)大津 | 55.0km | 2回 |
| (一部鉄道併行なるも特殊事情に依る) | ||
| 同茂岩 | 35.7km | 1回 |
| (同) | - | - |
| 同糠内 | 31.7km | 2回 |
| (同) | - | - |
| 同鹿追 | 34.2km | 3回 |
| 同雨宮温泉 | 12.8km | 4回 |
| 広尾ルベシベツ | 15.0kmkm | 2回 |
| 浦幌浦幌炭鉱 | 24.0km | 2回 |
| 帯広上美生 | 31.6km | 2回 |
| (一部鉄道併行なるも特殊事情に依る) | ||
| 同上士幌 | 37.8km | 2回 |
| (全線鉄道併行なるも、中間利用の特殊事情に依る) | ||
5、道北自動車株式会社
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 旭川鷹栖 | 16.5km | 3回 |
| 同上江丹別 | 21.8km | 2回 |
| (毎日2往復すること) | ||
| 同東神楽 | 13.3km | 2回 |
| 同志比内 | 23.7km | 1回 |
| 上川層雲峡 | 25.5km | 3回 |
| 士別温根別 | 18.5km | 2回 |
| 名寄美深 | 23.0km | 3回 |
| 枝幸雄武 | 54.2km | 2回 |
| 同小屯別 | 35.4km | 2回 |
| 稚内尻臼 | 32.8km | 2回 |
| 羽幌遠別 | 48.0km | 2回 |
| 沓形(利尻巡還)沓形 | 54.0km | 2回 |
| 香深船泊 | 20.0km | 2回 |
| 旭川当麻 | 16.5km | 5回 |
| (旭川当麻間2回旭川永山間3回) | ||
| 留萌増毛 | 18.0km | 3回 |
| 留萌市内 | 10.0km | - |
| 増毛別刈 | 6.1km | 3回 |
6、東邦交通株式会社
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 釧路昆布森 | 19.1km | 2回 |
| 同阿寒湖 | 81.8km | 2.5回 |
| (釧路舌辛間一往復) | ||
| 羅臼標津 | 47.9km | 1回 |
| 標津尾岱沼 | 14.0km | 1回 |
| 川湯駅川湯温泉 | 3.5km | 4回 |
| (主要列車のみに回数を減ず) | ||
| 弟子屈(直通)美幌 | 59.7km | 2回 |
| 阿寒湖北見桐生 | 20.6km | 2回 |
| 浜中霧多布 | 11.3km | 6回 |
| 釧路駅米町 | 3.0km | 45回 |
| 同鳥取 | 4.1km | 10回 |
7、北見乗合自動車株式会社
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 北見市(常呂留辺蘂)北見市 | 113.0km | 3回 |
| (北見留辺薬間鉄道併行するも、巡還線なるを以て存続せしむ) | ||
| 留辺蘂温根湯 | 12.0km | 6回 |
| 藻琴東藻琴 | 15.0km | 2回 |
| 置戸上置戸 | 11.5km | 3回 |
| 小清水止別 | 10.2km | 4回 |
| (小清水古樋間軍関係に依り、休止中なるも臨時に経営せしむる予定) | ||
| 留辺蘂二股 | 40.0km | 4回 |
| (六月下旬道路不良箇所修理完了次第、臨時として運行せしむる予定) | ||
8、札幌市
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 札幌駅(北8東1)北16東1 | 1.9km | 79回 |
| 同(北5東2)本村線 | 2.5km | 9回 |
| 同(北8)大覚寺 | 2.5km | 9回 |
| 大通西19(北1)琴似駅前 | 3.9km | 46回 |
9、函館市
| 延長 | 運行回数 | |
|---|---|---|
| 五稜郭停留所(亀田電車終点)五稜郭駅 | 7.5km | 98回 |
<<第4章 歴史的な大統合| 第6章敗戦から路線再建へ>>