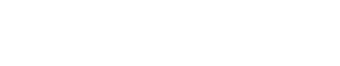第6章敗戦から路線再建へ
目次
窮乏のなか資材確保に努力
戦後、敗戦国民の間に「虚脱状態」という言葉が流行した。意欲、気力を失い、ぼんやり自失の状態を表現するものであった。戦争は終わったものの、人も街も虚脱状態であり、胃も心も飢えていた。「道南バス七十年史」は道内でも甚大な被害を受けた軍需都市室蘭の惨状にまで詳しく触れて、窮乏のなかで困難に打ち勝ち、バス事業の再建に励む人々をいきいきと伝えている。長文だが、再び採録したい。「室蘭も船舶の不足や燃料不足で、港に出入りする船はほとんどなかった。街も空襲や艦砲射撃の跡がそのまま残り、輪西駅の前には大きな穴が開いたままになっていた。日鋼、日鐵などは賠償指定工場となつたうえに、石炭の人手難からほとんど稼働できないといったことで、工場のすがたはまるでゴーストタウンのようになっていた。人口も大きく落ち込み、全体として室蘭はまったく火の消えた状態になってしまった。
胆振・日高・後志等の郡部は戦災はほとんど無かったが、近年にない低温と戦時中の人手不足のため作物の生育が悪く、この年の収穫は昭和11年の作柄の 65%で、明治以来という大凶作となった。
輸送の困難はバス業界においても大きなものがあった。戦時中は新車の割り当てがまったくないままに車両が老朽化し、室蘭市内ではわずか5台から8台程度の車両をやり繰りしながら運行している状態であった。おまけに敗戦直後は、室蘭に居住していた第三国人労働者が、停留場に立つ一般乗客を無視し、隊をなしてバスに乗り込み、これを拒めば窓ガラスを割りシートを切り裂くなどした。このような被害が起きても敗戦国の悲しさで泣き寝入りのほかなく、また、資材が無いために、窓にはベニヤ板を打ち付け、座席は板張りという状態で営業を続けざるを得なかった。
路線も整備が悪く、道路のあちこちは大小の穴があいて、雨が降れば水たまりになり、冬は積雪や吹きだまりのため車の運行は困難であった。車両の故障も続出した。しかし故障の修理も資材不足のため難しく、稼働できる車両は全社で昭和21年に21台、22年で31台にすぎなかった。このようなことから、当社の役員は道内各地をさがしまわり、あるいは根室から中古トラックを買い入れ、さらには軍用トラックの払い下げを受けるなど必死の工作を行ったが、バスに改造するにしても資材の人手が難しく、工場の関係者は苦労の連続であった。
日鐵が艦砲射撃で被害を受けたうえに、敗戦直後は操業を一時ストップしたことから、室蘭高圧燃料に対する石炭ガスは供給が止まってしまい、休業に追い込まれた。
昭知21年1月6日の室蘭民報は-(前略)日鐵のコークス炉は、昨年7月15日の艦砲射撃で破壊されたうえに、製鉄所のコークス炉がいよいよ作業不調となり、現在、町のコークス炉は、3千本のうち12、3本に火が入っているにすぎず、旧工場のコークス炉も戦争中 1基は大陸に移駐させ、残る2基も1基がすでに命がつきてしまったので、製鉄所内で使用するガスの供給にも不足を来すことになり、都市ガスもほとんど供給を停止されてしまったのである。道南乗合(注・当時の社名)では、とりあえず、ベンゾールその他による緊急運転を行っているが、何分の手持ち不足で本線に1-2台辛うじて運転するが、日鐵、ドック等の工員通勤時にはその1、2台でさえとられてしまうというわけで、『あてにならぬバス』となり、手も足も出ない有様である(後略)-とバス運行が危機に陥っていることを伝えている。
当時、ガソリン配給は全社でわずか1台分ぐらいしなかったので、車両の燃料の大部分は木炭と亜炭(注・炭化の低い低位炭)と薪であった。このためマキ切りやマキ割り、マキの乾燥などに多くの時間を費やし、また始業前に木炭のガスを作るため1時間も2時間も前からガス発生炉の調整をし、ファンを手回しで動かすなど、姶動前の作業がかなりの量にのぼった。とくに冬になると潤滑油が凍るため、朝早くから予熱しなければならぬという作業があり、また道路の除雪も除雪車がないため、現場に行ってみないと方法がつかないなど、現在では想像もつかぬような厳しい日々が続いた。
その上、木炭バスは出力が弱いために、穴に落ち込んだり、急な坂道にかかるとエンストを起こしたりして動かなくなり、乗客に降りてもらって後ろを押してもらったり、運転者や乗務員ばかりでなく、乗客までも泣かせることが少なくなかった。
このころは代用燃料としての木炭も近くからは手に入らず、その購入のため、担当者は遠く十勝、釧路、根室、北見方面の山岳地方までをかけ回った。しかし仮に入手したとしても鉄道輸送が難しく、到着までにはかなり多くの時間を要した。
このようなことから、運行キロ数も昭和21年には5 万3千kmにまで低下、23年にいたって辛うじて会社創立のキロ数(7万km)にまで回復した。したがって、乗車人員も昭和21年には年間330万人、1カ月わずか27万人にまで落ち込んだ。これは会社創業のときの見込みである年間600万人(室蘭520万人、登別50 万人、洞爺20万人、日高10万人)に対し55パーセントで、目標には遠く及ばなかった。
加えて、年に約10倍(1,000%)という破滅的なインフレのため、昭和20年、21年の運賃改訂を行なったものの人件費や資材の高騰には追いつけず、会社の窮状は惨憺たるものであった。株主に対しても20年からは無配となり、それが3年間続いた。
しかし、それは全日本的なものであった。戦時中の犠牲の体験はあまりにも生々しかった。従業員で軍隊からまだ復員していない者も少なくなかったし、その生死さえも不明であった。『それに較べれば、自分たちは文句をいえない。ともかくも、生き残って日本本土にいるものが日本の復興をはからなければならない』というのがその頃の人々の一般的な考えであり、『現在の生活がいかに厳しくても、明日を信じて最善を尽くす』以外に方法が無かった。そうしてそれが会社従業員の行動指針でもあった」
虚脱状態から徐々に再建へ立ち上がる決意にも触れて、バス事業を守り抜く人々の感動的な記録である。
再建指示に民主化政策の影響
やがて街の角々に闇市が立ち、軍服姿の復員青年らが米軍の放出物資や横流し食糧を並べて売り始め、そこばかりは異常な活気がみなぎった。配給は当てにならず、農家に買い出しに行く人々がくたびれたバスや列車にあふれた。輸送需要は日に日に増えるばかりだった。運輸省が、占領軍の指導により陸運統制令を廃止し、戦時中の非常措置に基づく制限を解除、路線の再建を指示する次のような「旅客自動車運輸事業再建計画に関する件」を出したのは昭和20年10月であった。
- 現在休止中の路線にして国民生活の安定ならびに経済再建上必要なるものは地方事情勘案のうえ漸次その必要数に応じ再開せしむること。
- 工員輸送路線は平和産業に転換する事業の工員を輸送する路線を除き廃止せしむること。
- 旅客自動車運輸事業者の兼営せざる特定旅客運送事業は付近の旅客自動車運輸事業をして経営せしむること。
この通達には、軍需輸送重点の戦時中なら目にすることのなかった、国民生活とか平和産業とかの文字が見え、ここにも占領軍の民主化政策の影響が読み取れよう。
道内バス、事業再建に立ち上がる
運輸省の通達に応じて当時の北海道乗合旅客自動車運送事業組合はバス事業の再建案の検討に入り、 12月、再建5カ年計画をまとめた。昭和21年度までを計画樹立の年とし、翌年から実行に入り、24、25 年度で合理的運営の確立を目標に、順次、現行路線の増強、休止路線の復活、新路線の開拓と事業を拡大してゆくという計画であった。そのためには道路、車両、燃料、資材、資金などの面で自主的な努力を続けるとともに、関係方面へも協力を強く要請している。いわば再建のための運動方針とでもいうべき呼びかけであった。(詳細は下欄)
ここから読み取れるのは、車の老朽化、燃料の慢性的な不足、資材の入手難、改善されぬ道路事情、資金の不足など、困難な問題が山積している様子ばかりで、たちどころに着手して実現できるような課題は少なかった。しかし、第4年次以降に「躍進」の文字が現れ、再建へかける意気込みは伝わってくる。
これにもとづき、道内の各バス会社も、それぞれ早期に再建計画をたて実行することを申し合わせた。まず休止路線の復旧が先決であった。だが、どこから手をつけていいのか。
北海道乗合旅客自動車運送事業組合のバス事業再建計画(昭和20年12月)
1)年度別目標
- 準備年次 昭和20年度 計画樹立の準備検討
- 第1年次 同21年度 計画樹立
- 第2年次 同22年度 実行第一年
- 第3年次 同23年度 運営強化への推進
- 第4年次 同24年度 合理的運営への躍進
- 第5年次 同25年度 合理的運営への徹底
2)基礎的総合計画
- 現行路線の増強=車両の増備による運行回数の増加を図る
- 休止路線の復活=可及的に休止路線の復活を図る
- 新路線の開拓=道の開発計画に即応する新路線の開拓を図る
3)附随的総合計画
<<道路条件の解決>>
- 自力をもって解決し得るものは、経費又は労力を負担して積極的解決に努力する
- 町村民の理解ある協力により、改修促進を図る
- 現地土木現業所に懇請して改修促進を図り、これに協力する
- 北海道庁及び道議会に陳情して、改修を推進する
<<車両事情の解決>>
- 現有車両の整備に全力を傾注する
- 新車の配給を要請する
- 進駐軍車両の払下げまたは貸下げを要請する
<<燃料及び油脂事情の解決>>
- 代用燃料(木炭・薪)の自営生産を図る
- 電気自動車の使用研究
- 燃料・油脂の消費節約の研究
- 絶対必要所量の配給方を懇請する
<<タイヤー・チューブ事情の解決>>
- タイヤー・チューブの消費節約の研究
- タイヤー工場の道内誘致を図る
- 絶対不足数の増配方を懇請する
<<金融事情の解決>>
- 増資による解決
- 融資の途の確立を図る
苦心の更生車や『囚人護送車』も
 すべてにわたって物不足は深刻であったが、中でもバス事業の命である車両の老朽化対策が急がれた。さまざまな工夫がこらされ、また新車の出回りがわずかなりとも意外に早かったことを「北海道中央バス五十年史」は次のように記録している。
「新会社発足時の保有車両数は175両だが、すでに老朽化していて使用不能なものが多く、使用できるものは148両しかなかった。これらのバスはほとんどが木炭車に改造された『代燃車』で、数両しかなかった薪バスも、その後、廃車または木炭に改造されて姿を消している。
すべてにわたって物不足は深刻であったが、中でもバス事業の命である車両の老朽化対策が急がれた。さまざまな工夫がこらされ、また新車の出回りがわずかなりとも意外に早かったことを「北海道中央バス五十年史」は次のように記録している。
「新会社発足時の保有車両数は175両だが、すでに老朽化していて使用不能なものが多く、使用できるものは148両しかなかった。これらのバスはほとんどが木炭車に改造された『代燃車』で、数両しかなかった薪バスも、その後、廃車または木炭に改造されて姿を消している。
新車(ガソリン車)の出回りは割合早く、終戦の翌年からで、当社はこの年初めて5両を購入している。しかし路線が拡大するにつれて車両不足が深刻となり、これを補うため当社は、軍放出のトラックを改造したボンネット型の『更生車』と称するバスを昭和23 年ごろから数年間、札幌、滝川の両整備工場で製作、また滝川工場では『囚人護送車』と呼ばれた古トラック改造のバス、小樽工場では廃車のボディを再利用した『再生車』も製作した。これらの手作りによる改造バスは、正確な記録がないため何両作られたか不明だが、木炭バスとともに活躍、やがて国産自動車メーカーの新車生産が本格化するにつれて姿を消す運命をたどった。
当社に初めてディーゼル車が入ったのは昭和23年で、小樽でボンネット型のディーゼルバス2両(いすゞ、中三方シート、定員48名)を購入したという記録が残っている。ディーゼル車は馬力が強くて燃費が安いことから、ガソリン車にとってかわって急速に普及し、現在ではほとんどディーゼル車になっている」
「田舎のバスはおんぼろ車」という歌があったが、創意と工夫でバス車体の整備が進み、公共の足としての任務が確かなものとなってゆく様がしのばれる。
米軍車両の払い下げで一息
平和の回復後、自動車工業の復活は意外に早かった。工場の戦災が最小限であったこと、占領軍からの原料の使用が許され、バス、トラックで昭和21年度には14,158両、22年度には9,709両、23年度には 17,564両の生産を挙げている。新車の配分については、バス業界の代表も参加して中央、地方ごとに配給委員会が割り当てを決めたが、昭和24年度には生産が上昇して割り当て制度は不要になるほどであった。
また車両不足を救ったのは占領軍の自動車払い下げであった。昭和21年8月、トラック4,700両、トレーラー5,159両が国と民間業者に貸与された。翌年には都市交通緩和のため、このうち東京郊外の4バス業者に105両が払い下げられた。さらにバス用として米軍アンヒビアン(水陸両用車)440両の払い下げが決まり、全国の業者から希望を集めて配給された。この車にはガソリンとタイヤの裏付けがあるのが特典と言えた。東京急行電鉄がもっとも多い45両、 10両以上では札幌市営が15両の割り当てを受けている。
外国依存のタイヤ、チューブ事情はなかなか改善されなかった。これも占領軍の好意で生ゴムの放出を得て、昭和23年度からようやく好転を見たが、需要を満たすものでなく、日本乗合自動車協会は昭和 24年2月、バス用タイヤの大量放出を求めて、当局に次のような緊急の訴えを行っている。
「バス事業にありては1カ月の必要量7,681本に対する配給量が2,609本で要望量に対し33.9%にしか当たりません。その結果、実在車数12,890両に対する実働は9,201両で71.3%しか働いていない実情であります。これに対し業者は定期運行の責任を果たすためにタイヤの愛護運動、更新再生に対する適当な時期の選択等、これが命数の延長に最善の方途を講ずる一面、中にはやむなく正規外のルートから融通するという苦肉策を講じている者もあるやに想像されますが、それも最近の情勢ではすでに底をついた模様であります。したがってかかる事態が今日のまま進行するものとすればバス事業は遂に最悪の段階に突入するは必至の成行であります。よって、バス事業の壊滅を未然に防ぎ、その復興整備を促進するため万難を排してタイヤを一時的に大量放出せられるよう格段の御審議を賜りたいと存じます」
このころのタイヤの耐用命数は2万km程度とされ、更生・延命策が真剣に行われた。人絹コードが綿コードに変わってから耐用命数も3万km(都市内で5、6万km)に伸び、さらに通産・運輸共同省令で「補修用タイヤ、チューブ配給規則」が公布され、販売業者の登録制、フリークーポン制による自由競争、修理施設の整備などを指導したことから、タイヤ事情はようやく改善された。
着実に進む路線の再建
こうした業界、各社のさまざまな努力と工夫の結果、北海道旅客輸送協会(後述・昭和23年1月設立)がまとめた年次別の路線バス休止状況(毎年8月現在)をみれば、終戦当時は58%であったのが年を追うごとに回復し、昭和22年には31%となり、24年には13%、26年には5%と進んで、当初の5カ年計画に比べれば多少遅れたとはいえ、25年には路線再建がほぼ達成されたのであった。
代燃車からの転換は遅れる
戦争が終わってもガソリンの供給はなかなか増えなかった。これはそのすべてを輸入に依存するため、米国の好意によるガリオア資金のほか外貨はないので、やむをえないことであった。自動車全体のガソリン配給量の推移を見ると、昭和20年には44,745キロリットルまで落ち、21年度には120,121キロリットル、22年度が228,110キロリットル、23年度が 273,588キロリットルと徐々に増えているが、昭和12 年度の1,169,462キロリットルに比べると、わずか 1、2割にすぎない。このため代用燃料車からの転換は進まなかった。
バス事業全体での昭和23年5月現在の代燃車統計(単位・両)を見れば
| 木炭車 | 液化、圧縮ガス車 | 薪車 | 電気車 | 石炭、コーライト車 |
|---|---|---|---|---|
| 5,051 | 241両 | 1,839両 | 268両 | 239両 |
| 計 7,638両 | ||||
これに対し、ガソリン車は3,240両であった。
ガソリン供給増は昭和25年から
運輸省の方針は、配給の復活したガソリンは運行回数の増加や休止路線の復活等、新たな必要に当てるべきだというものであったし、また22年1月には連合軍最高司令官の覚え書で代燃車のガソリン車への転換は許可しないと明示された。8月には経済安定本部長官の「石油製品配給要領」通達で、ガソリン車は国家再建のため特に必要なものに限られ、登録を受けた車は前面ガラスに、ガソリン車は丸に揮の字、ディーゼル車は丸に軽の字の標識をつけなけらばならないとされた。この配給要領は24年11月に割当規則に変わって廃止されたが、登録制度は石油製品の需給が安定するまで続いた。
バス事業への供給量の推移をみると
| 昭和23年 | 昭和24年 | 昭和25年 | 昭和66年 | |
|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 31,826kl | 38,737kl | 49,451kl | 100,419k |
| 軽油 | 3,087kl | 12,870kl | 31,230kl | 70,943kl |
となっており、昭和25年度から好転し始めたことがわ かる。特に軽油の増加は著しいものがあった。これ は軽油車については一般貸切用、不定期用を除いて 制限なく登録が認められるようになったためであっ た。一般貸切用、不定期用についても不要不急の用 途に使用しないものに限り登録が認められた。
すでに25年1月から太平洋岸石油精製工場の再開 が許可され、ポンド地域からの原油の輸入も許され ていた。
バスこそ優先してガソリン車へ
昭和26年4月から連合軍の覚え書で代燃車の石油燃料車への転換禁止が解除された。ここで日本乗合自動車協会は佐藤栄作会長名で次のような陳情を関係大臣に行った。これは戦中戦後、さまざまな困難を強いられながらも国策輸送の任務に励んで来たバス業界が、公共優先ならばバス業界こそガソリン転換も優先すべきだと、強くその正当性を主張した文書であり、全文を採録したい。
[バスの代燃を石油燃料に転換せられたき件]
今回石油製品の統制が進駐軍から日本政府の手に移されたことは、石油事情の好転を契機とし、末端消費者をして縦横に手腕を振わしめんとする積極的な意図に出たものと考えられ、まことに喜びに堪えません。
御承知の如く、バス事業は戦時中卒先して国業に順応し、これがために生ずる諸々の悪条件と膨大な赤字を忍びながら、ひたすら公共機関としての使命を果たすことに努めてまいりました。しかも終戦後は進駐軍の覚え書により石油燃料への転換が禁止されたため、その後多少の緩和をみたとはいえ、非常に不利な立ち場に置かれたまま今日に至っております。従って今次石油燃料割当の構想は、バス事業の特殊性並にわが国文化水準向上のために、この機会においてバスの代燃をすべて石油燃料に転換すること第一義とし、併せて事業の助成擁護に資せられるよう御考慮願いたく、別記理由書を添え陳情いたします。
理由書
- バス事業今日の経営難は戦時、戦後相当長期間にわたり、代燃車一色の経営を行って来た結果でありますから、この際他の業種に優先して石油燃料への転換を行わしめられるものと信じます。
- バス事業は昭和23年7月設定の公定運賃を基準としております。しかるにその後における著しき諸物価の騰貴、殊に最近国際情勢の変化に伴うタイヤ、チューブ、車両、燃料その他諸資材の暴騰は一切現行運賃に織り込まれておりません。もしこの際石油燃料への転換が行われるものとすれば、燃料面の経済、車両その他資材面等からみて経営上の赤字を相当克服することができ、業界は全幅の期待をこの点にかけております。
- バスは出発及び到着時刻のみならず、中間多数の停留場における定時発着を生命といたしますから、故障率が高く、かつ始動に困難な代燃の使用は自動車各業種中最も不適とするところであります。殊に通勤通学のラッシュ時における故障や延着は国家の産業文化に重大影響を与えることは申すまでもありません。
- 戦後既に6年、総ての交通機関が設備においてもスピードにおいても、また時刻の正確さにおいても既に戦前の水準を取り戻している今日、独りバスのみが代燃の歪められた姿で走り、少しの坂路にも困難するということは、今日の常識では最早納得し得ないところかと存じます。
- 要するに、バス代燃車の石油燃料への転換は(1)経営難よりする業界の危機を緩和し(2)観光日本の体面を保ち、文化水準の向上を図り(3)ダイヤの正確を期し(4)輸送の増強を図り(5)休止路線の速かな復活に備える 等、幾多の重要性を持っております。従ってこの機会においてはわれわれ宿積の願望を容れられ、バス事業復興助成のために格段の御同情を御願いたす次第であります。
バス業界が、誇り高くその公共性と任務の重要性とをアピールした宣言ともいえる文書であろう。
本道でも石油への転換終わる
このような働きかけから代燃車から石油車への転換に弾みがつき、昭和26年度には全国で44,700両の転換が完了した。次の全道営業バス車両燃料別推移表を見ると、昭和22年5月にガソリン車19%、代燃車81%だったものが、同27年にはガソリン車58%、軽油車42%となり、代用燃料車がまったく姿を消したことがわかる。
戦中戦後の輸送を担った代燃車は、老兵のように静かに消えてゆき、新しい時代がやって来ていた。
| 燃料別 | 22年5月 | 23年5月 | 24年9月 | 25年10月 | 26年10月 | 27年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソリン | 68両 | 144両 | 282両 | 320両 | 471両 | 532両 |
| 軽油 | - | - | 61両 | 197両 | 297両 | 390両 |
| 木炭 | 225両 | 233両 | 142両 | 115両 | 19両 | - |
| 薪 | 41両 | 24両 | 24両 | 24両 | 1両 | - |
| メタンガス | 30両 | 6両 | 6両 | 6両 | 2両 | - |
| コーライト | 1両 | - | - | - | - | - |
| 電気 | - | 9両 | 16両 | 22両 | 1両 | - |
| 代用液体 | - | - | - | 4両 | 3両 | - |
| 合計 | 365両 | 416両 | 531両 | 688両 | 794両 | 922両 |